スマートフォンを活用した縦型ショート動画は、視覚的にインパクトを与えるための強力なツールです。特にSNSで注目を集めるためには、短時間で視聴者の心を掴む映像作りが求められます。
この記事では、スマホを使って縦型ショート動画を効果的に撮影するためのコツや注意点について解説します。具体的には、撮影環境の整え方やブレ対策、明るさ調整のポイントに加え、編集前に確認すべき大切な要素を紹介します。
これらのテクニックを押さえて、より魅力的な映像を簡単に制作できるようになりますので、SNSでの注目を狙いたい方に最適な内容です。
目次 [目次を見る]
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
ショート動画とは?

スマートフォンで手軽に鑑賞される映像形態となり、多くのプラットフォームで活用されています。短い秒数でも要点を伝えられる点が魅力です。情報を効率よく発信しやすく、多様なジャンルで拡散されやすい特徴があります。誰にでも制作しやすいため、ビジネスや趣味など幅広く利用されています。
縦型動画が標準
スマートフォンを縦向きに使う人が増え、SNS上での映像も縦長が当たり前になっています。この構図には、人の顔や商品を強調しやすい利点があります。縦長画面で映像を見ると、余計な背景を切り取りやすく、視聴者は内容に集中しやすくなります。
宣伝活動でも多用され、テキストやグラフィックを重ねる際も見やすさが向上します。たとえば、料理動画なら、材料や手元を効果的に映し出し、調理手順をわかりやすく整理できる点が特長です。
一方で、横向きに撮影された素材を再編集する場合はトリミングが必要になりますが、視覚的なインパクトを高めるためにあえて縦型を選ぶ制作者も多いです。撮影段階で縦構図を意識できれば、編集作業を効率化でき、視聴者に合わせた映像を届けやすくなります。
継続的に視聴者の目を引くためにも、縦型を基本とした設計が求められています。
テキストやイラストだけでも対応可能
テキストやイラストだけの構成でも映像として成り立つ場合が多いです。動きを加えることで視線を誘導したり、要点を強調したりできる点が特長です。
美しいフォントや効果的な配色を使えば、写真を使わずとも視聴者は飽きにくくなります。イラストをスライドさせたり拡大表示したりすると、手軽に視覚的変化を与えられます。
図解やマンガ調のアートでストーリー性を持たせれば、内容が分かりやすく印象に残りやすいです。動画編集ソフトやアプリを使えば、文字やイラストにさまざまなエフェクトを付けるのも簡単です。制作コストを抑えつつ幅広いテーマに対応しやすいため、個人の発信から企業の広告まで活躍の場も広いです。
背景音楽やナレーションを入れなくても内容を伝えることができるため、静止画の延長線として気軽にチャレンジしやすいです。
ジャンルは幅広い
縦型のショート動画はジャンルを選ばず、多彩なテーマで作られています。商品紹介やメイク動画、ダンスやレシピまで幅広い分野で活用されています。
専門知識がなくてもスマートフォン一台あれば手軽に制作できる環境が整っており、短い時間で情報を詰め込むことができます。視聴者の興味や関心を素早く引き出せるのも強みです。
一瞬で目を引くアイキャッチを用意し、要点を明確に示すことで、最後まで見てもらいやすくなります。趣味の記録から商品レビューまで幅広く共有されるため、独自の切り口を盛り込むと他との差別化ができるでしょう。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
縦型動画の特徴と種類

縦型動画には、スマートフォンでの視聴に適した見やすさと集中しやすさがあります。撮影や編集の方法によって多彩なバリエーションが生まれ、ライブ配信や広告など、応用の幅も広いです。
フルスクリーン型(縦型)
画面全体を縦向きで覆うフルスクリーン型は、視聴者の没入感を高めやすいです。雑多な背景を排除することで、目を引く内容に集中させ、印象に残る映像を届けやすくなります。
テロップや字幕を入れる位置にも余裕があり、テキストやアイコンを直感的に配置できます。全身を映したダンス動画や、大胆に商品を映し出すプロモーションにも活用されています。
一度に表示される情報量が多いので、細部まで工夫を凝らしておくと訴求力が増します。撮影の段階で余白をきちんと確保し、編集時に文字やイラストの配置を最適化すれば、縦型ならではのインパクトを生かせます。
視覚だけでなく音声演出を添えると、さらに魅力が引き立ちます。視聴者がストレスなく理解できる構成を心がけることで、満足度の高い動画に仕上がります。
横並び型(横型)
横型は伝統的な映像の比率でありながら、縦型に変換しやすい柔軟さがあります。従来のテレビやパソコンディスプレイでも自然に視聴できるため、幅広い層に適応する点が特徴です。
編集時に左右の空間を活かせば、文字情報やサブ映像を持たせやすくなります。例えば、画面の片側に商品名、もう片側に使用方法を並列表示すれば、視認性が高い構成が可能です。
ライブ配信やイベント映像も、横型で撮影した素材を切り出せば縦型用に再編集しやすくなります。最初から横基準で撮影する場合は、場所や被写体を広く取り込んでおくと柔軟な加工に対応できます。視聴端末に合わせて最終調整を行えば、マルチプラットフォームへの展開がスムーズになります。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
スマホでバズる縦型動画の撮影のコツ

縦型を意識した撮影では、被写体の配置や背景の整理が大切です。カメラを安定させ、見せたい要素を中心に収めると見やすい映像になります。余白を残しすぎると情報が伝わりにくくなります。
撮影時にあらかじめ構図を考えておくと、編集がスムーズになります。
不要な空白をなくして撮影する
縦型動画では画面上下のスペースが限られているため、空白が多いと内容が希薄に見えてしまいます。被写体を枠内にきっちり納めることで、伝えたい情報を確実に視聴者に届けられます。
たとえば人物を撮る場合は、頭上や足元を広く空けすぎないよう気をつけると、集中度が増します。背景に余計なものが映り込みそうな時は、カメラ位置を少し変えたり、画角を調整したりして無駄を削る工夫が必要です。
コンテンツを最適なバランスで構成できれば、見た目がすっきりして伝わりやすくなります。編集時にテロップなどを挿入する予定があるなら、あらかじめ配置を想定した撮影を心がけるとスムーズに進みます。
できるだけ1テイクで長めに撮影する
一度に長めのテイクを撮ると、編集作業で細かく切り出す余地が生まれます。複数回撮影をやり直す手間を省けるうえ、自然な流れが保たれやすい利点もあります。
特にセリフや動きのある場面は、連続で記録しておくと使いたい部分を後から最適に選べます。長回しの映像は尺が長くても、不要な部分をトリムして短縮すればショート動画の形に仕上げやすいです。
作品の雰囲気を途切れさせずにまとめることで、視聴者にスムーズな印象を与えることができます。環境音などを拾いやすい場合は、一括で録音しておき編集時に音声を調整すると品質向上に役立ちます。
少し余裕を持って広めに撮影する
撮影時に対象をぎりぎりのサイズで収めると、後からテロップやアイコンを配置しづらくなります。周囲に余白を確保しておくと、編集で拡大やリフレーミングを行う際に画質が劣化しにくいです。
撮影環境によっては想定外の動きや要素が映り込むことがあるため、広めに撮るとトリミングの自由度が高まります。動く場面や素早い動きの演出では、多少距離を取って撮ると被写体が切れずに収まります。
最終的に配信プラットフォームに合わせたアスペクト比に調整しやすいのもメリットです。撮影時は映り込む背景にも目を配り、後で加工しやすい映像素材を残すことが効率化につながります。
レンズの焦点距離を考慮して撮影する
使用するレンズの焦点距離によって、画角や被写体の見え方が変化します。広角レンズを使うと背景が多く映り込み、狭い場所でも撮影しやすい反面、被写体が歪みやすくなります。
望遠側で撮ると背景が圧縮され、余計な要素を整理しやすいですが、手ぶれが目立ちやすい場合もあります。自分の撮影環境や映したい内容に合わせて、どの画角が適切かを検討すると映像の完成度が高まります。
人の表情や細部を捉えたいなら、被写体に寄るか焦点距離を調節して鮮明に撮るとわかりやすいです。
手ぶれを最小限に抑えて撮影する
手ぶれが多い映像は視聴者に酔いを感じさせたり、情報を正確に伝えにくくなります。スマートフォンなら両手でしっかり支え、そこで身体を固定すると安定感が増します。
カメラの手ぶれ補正機能がある場合は有効に活用すると良いです。動きながら撮る際は、歩幅を小さくする、フィギュアのようにゆっくり動くなどの工夫で揺れを抑えられます。
編集段階で手ぶれ補正をかける方法もありますが、撮影時から配慮するほど仕上がりが自然になります。穏やかな映像は情報を受け取りやすく、背景まで見やすいです。
十分に明るい場所で撮影する
暗い環境で撮影すると、映像がざらつきやすく、重要な部分がはっきり映らないことがあります。明るい場所なら被写体の色味や表情がより正確に再現され、説得力のある映像に仕上がりやすいです。
自然光を活用できるなら、窓辺や屋外での撮影を検討するのも手段の一つです。照明機材を使う場合は、被写体に均一な光を当てるよう配置すると陰影がつきすぎず見やすいです。
光源が強すぎる場合はレフ板やディフューザーを使って調整し、映像全体を柔らかい印象にすることができます。撮影後の編集で明るさを補正する方法もありますが、最初から十分な照度を確保すると画質低下を防げます。
カメラを固定して動く被写体を捉える
動きのあるシーンでは、カメラを固定することで被写体の動きを明確に追いやすいです。ゆったりした移動やダンスパフォーマンスなど、画面内で動きが映える演出をしやすいです。
カメラがぶれると主役がどこにあるのか分かりにくいため、視聴者の集中力を損ないかねません。固定撮影は編集時にエフェクトやカットを加えやすく、情報を整理した映像が作れる利点もあります。
動きの速い被写体を撮る場合でも、背景との相対的なブレが抑えられ、視認性を保ちやすいです。
三脚を使用して安定した撮影を行う
三脚を使うと安定度が増し、撮影者の体勢による振動を大幅に軽減できます。特に長時間の撮影や定点観測的なシーンでは、三脚の有無が画質に大きく影響します。
構図を決めたまま撮影を続けることで、観る側は集中して内容を理解しやすくなります。被写体がイベントや人の集合などの場合でも、最適な高さと角度を保持しやすいです。
三脚はサイズや重量のバリエーションが多く、屋外撮影にも対応しやすい携帯性の高いモデルもあります。安定した土台を確保するほど映像のクオリティが上がり、編集作業でも微調整が容易になります。
カメラを動かす時は、ゆっくりと滑らかに動かす
カメラを急に振ると、視聴者はフレーム外の情報を急に見せられて混乱する可能性があります。動かす際は一定の速度を意識し、滑らかにパンやチルトを行うと自然な映像に仕上がります。
被写体を画面中央に捉え続けるのではなく、動きやストーリーに合わせたフレーミングを心がけると伝わりやすいです。
予想外の動きに対応する際は、素早く振らずにほんの少し機敏に向きを変える程度で視聴者を誘導できます。
編集で補正可能な場合もありますが、撮影時点で丁寧に動かすほど無理のない映像が期待できます。ゆっくり動かすことで、細部まで視認でき、重要な場面を見逃しにくい利点があります。
適切な明るさに調整する
明るさが過剰になると白飛びを起こしてディテールが失われ、逆に暗すぎるとノイズが増えて粗く見えます。現場の照明や自然光の状態を見極め、必要に応じて露出補正を行うと最適な映像が得られます。
スマートフォンでも、撮影時に明度をスライダーで調節できる機能がある場合は活用しましょう。光源の方向や強さによって影ができるので、撮りたい対象の一番見せたい面を程よい光で照らす工夫が必要です。
複数の光源がある場合は、メインライトと補助ライトのバランスを調整して、コントラストを抑えた映像に仕上げることが求められます。
適度な明るさを保つと、色彩や質感が自然に表れ、視聴者の理解を助けます。
最適な撮影設定を選択する
動画の解像度やフレームレートは、目的や配信先に合わせて決定することが大切です。SNS向けのショート動画なら、高解像度すぎるとデータが重くなり、快適に視聴できないため、適度な画質を選ぶことが重要です。
動きが激しいシーンではフレームレートを上げると滑らかに見え、ゆったりした内容の場合は標準設定でも十分に伝わります。端末やカメラの特性により画質や色味が異なるため、事前にテスト撮影して最適な設定を探る工夫が必要です。
ホワイトバランスを設定すると、映像全体の色調が安定し、見やすさが向上します。制作意図に合わせて撮影設定を吟味し、編集から公開までストレスなく進められるようにしましょう。
多様な角度や構図で撮影する
同じ場面でも視点を変えるだけで、新鮮な映像表現が可能です。低い位置から撮れば迫力が増し、高い位置から俯瞰で撮れば全体の配置を一覧できます。横移動や斜めのアングルを取り入れると、自分たちだけの独自性を演出しやすくなります。
被写体のサイズ感を変えたり、背景の要素を活かした構図を試みると視聴者に強い印象を与えることがあります。複数のアングルで撮影しておけば、後でつなぎ合わせてリズム感のある映像に仕上げられます。
構図の引きや寄りを活用し、重要なディテールと全体像のバランスを整えると効果的です。
寄りや引き、アングルに気をつけて撮影する
寄りすぎると被写体の一部しか映らず、情報量が不足する場合があります。引きすぎると背景ばかりが目立ち、主題が埋もれてしまうこともあります。
バストアップや全身など、どの部分を中心に見せたいかによって最適な距離が異なります。角度の工夫も映像の印象を左右し、少し斜めに構えるだけで雰囲気が変わります。
撮影対象を複数回異なる寄り引きで押さえると、編集段階で場面転換にバリエーションが生まれます。
最適なフレーミングを見つけるには試行錯誤が欠かせませんが、それが完成度の高い縦型動画へとつながります。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
縦型動画を撮影・編集する前に確認すべき4つの準備と注意点

事前に準備を整えておくだけで、撮影や編集工程がスムーズになります。運用目的を明確にし、想定の視聴環境に合った計画を立てると完成度が高まります。意外なトラブルを防ぐためのチェックリストを作成しておくことも有効です。
SNSプラットフォームと「カバー範囲」の確認
SNSによって表示領域や推奨のアスペクト比が異なるため、事前の把握が必要です。スマホアプリでプレビューしてみると、テロップやタイトルが見切れたり、アイコンが隠れたりするケースを確認できます。
InstagramのストーリーズやYouTube Shortsなど、それぞれの推奨サイズを踏まえて撮影すると余計な修正を減らせます。投稿後に端末ごとに表示範囲が変わることもあるため、重要な情報は画面中央付近に収める工夫が好ましいです。
複数のプラットフォームで同じ動画を使いたい場合は、あらかじめ安全エリアを考慮しながら撮影すると効率が良いです。仕様変更も頻繁に起こり得るので、こまめなチェックで対応策を練るとスムーズに発信できます。
シナリオ(台本、絵コンテ、文字コンテ)の整備
撮影前にストーリーや構成を明確にしておくと、現場で迷う時間が減ります。セリフや演出のタイミングを台本の段階で決めておけば、撮影と編集が隙間なく進められます。
絵コンテや文字コンテがあると、ビジュアルイメージを共有しやすく、関係者と認識を合わせやすくなります。また、シナリオが定まっていれば尺の無駄を省け、ショート動画でも的確に内容を伝えられます。
台本に沿って撮影する際、実際の現場で出てきた工夫点などを逐一メモしておくと後で修正しやすいです。完成度の高い動画は準備段階を丁寧に行うことで得られます。
SNSでの編集エリアをあらかじめ決めておく
動画をアップロードすると、アプリ内でテキストを追加したり、スタンプを貼ったりする機能を使うことが多いです。事前にどこに文字を重ねるか、どんなエフェクトをかけるかを把握しておくと撮影時から無駄が減ります。
上下や左右にアプリ特有のボタンや説明が重なる場合があるため、重要な情報が隠れない安全エリアを意識することが大切です。テキストサイズや表示位置は、端末によって見え方が微妙に変わるため、汎用的に見やすい配置を検討しましょう。
編集工程を簡略化するには、ある程度テンプレートを用意しておくとスピーディに仕上げやすくなります。あらかじめイメージを共有しておけば、撮影スタッフと編集担当が円滑に連携できます。
音声の有無を事前に確認する
動画を静止画的に使うならBGMやナレーションは不要な場合もありますが、音声があると臨場感が高まることが多いです。SNSでミュート再生されるケースを想定して、テキストで情報を補足するかどうか決めておきましょう。
撮影時に周囲の雑音が大きい環境だとクリアな音声が録れないため、マイクや録音設備を整えるか検討する余地があります。特定のBGMを使うなら著作権や使用許諾も事前に確認が必要です。
音声を入れる前提で撮影した映像は、音のズレやリップシンクが重要になるので、後編集との兼ね合いを把握しておくと仕上がりが自然です。無音でも伝わる構成を念頭に置けば、音声が再生されない視聴環境でもメッセージを届けられます。
Shopifyやその他ECの制作・運用・保守について、お気軽にご相談ください。
連絡は問い合わせ・無料相談・無料お見積りよりどうぞ。
まとめ:スマホでバズる縦型ショート動画の撮影のコツ、注意点を解説

縦型動画はスマートフォンユーザーに親和性が高く、多くのジャンルで応用が利く手法です。撮影や編集のコツを押さえておけば、魅力的なショート動画を作りやすくなります。
十分な準備を重ねることで完成度を向上させることが可能です。まだ迷いがある方は、専門家に相談して実践的なアドバイスを受けると効果的です。次は実際に撮影・編集を行い、その可能性を確かめてみてください。
具体的な成果を出したいなら、企画段階からプラットフォームとの相性も検討すると良いでしょう。
Shopify制作のお見積もり・ご相談
また、初めてのお取組みで不安のある方などもご不明点などはお気軽にご連絡ください。






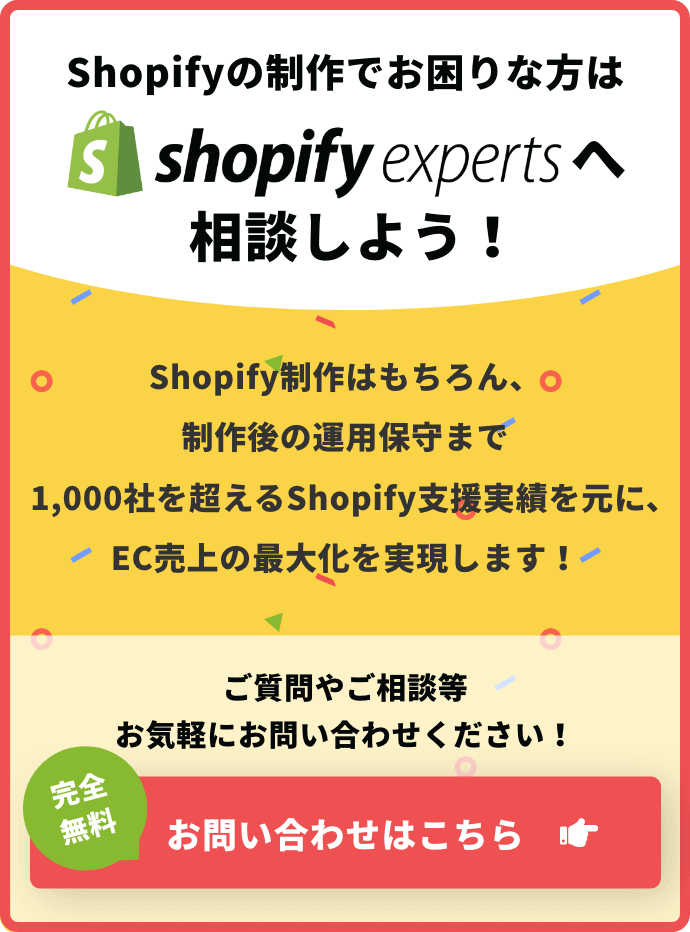



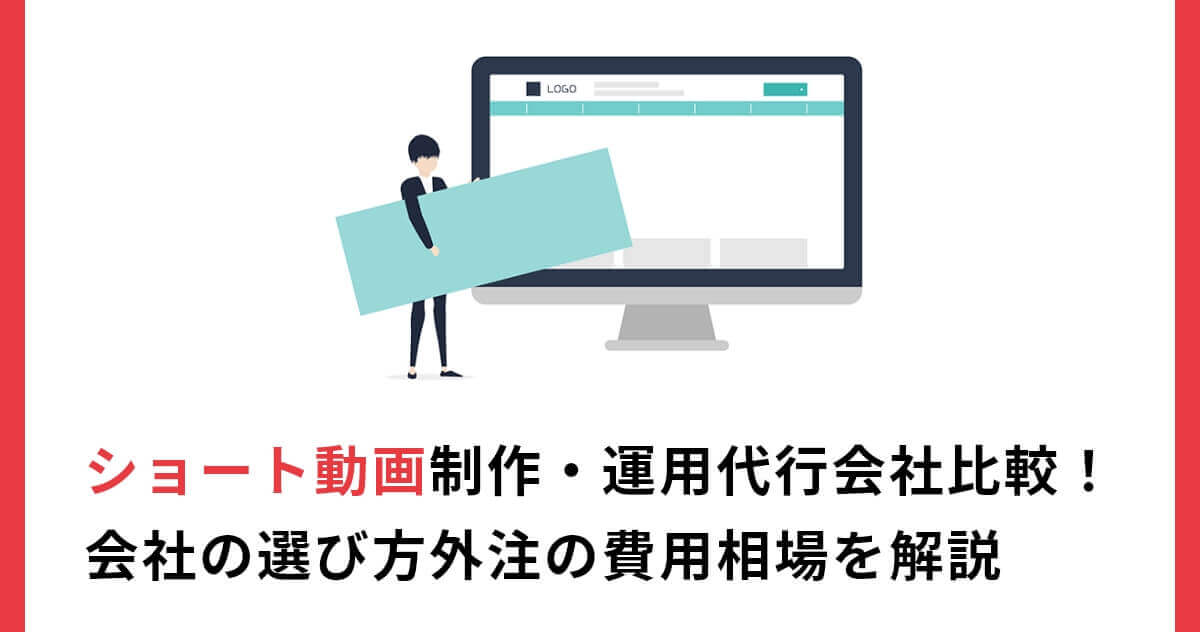



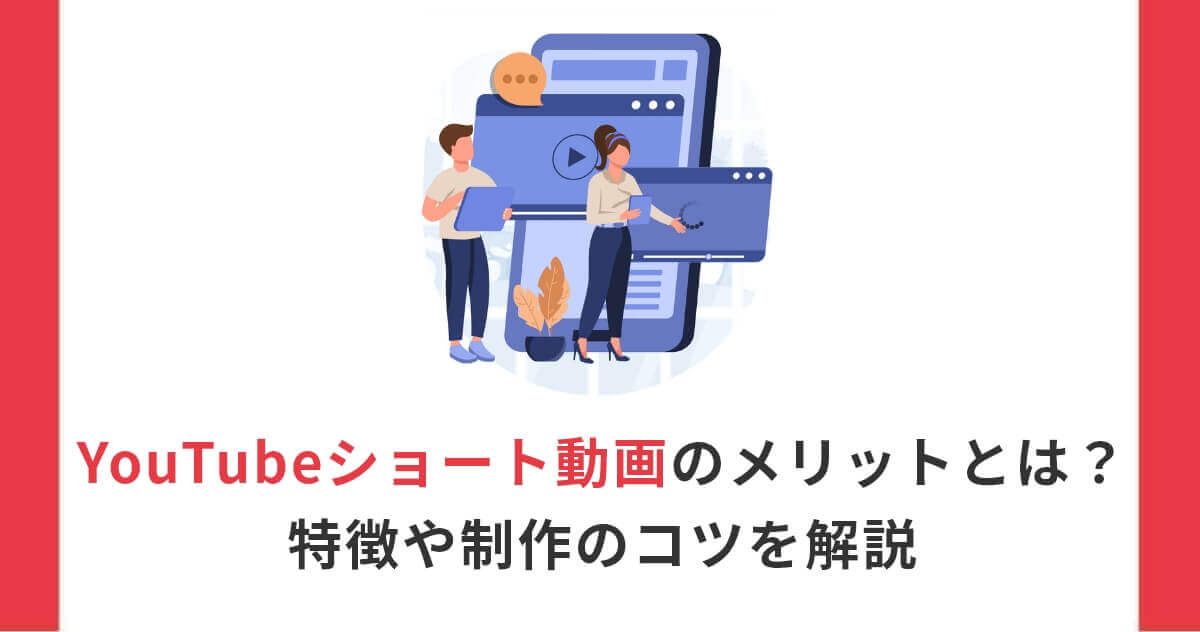



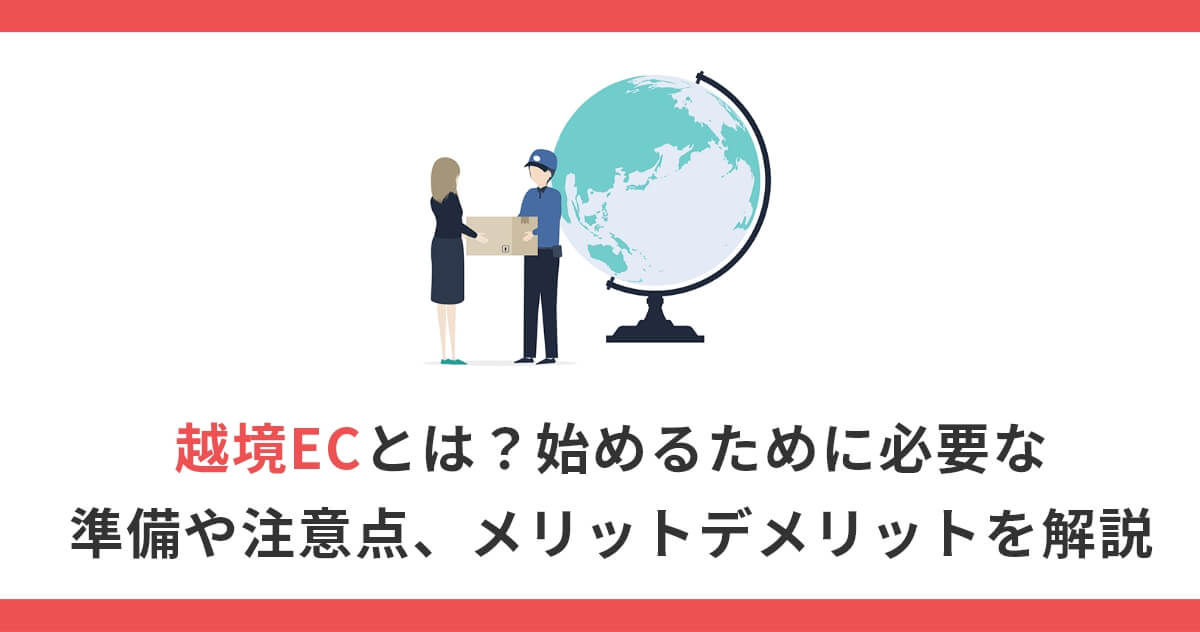



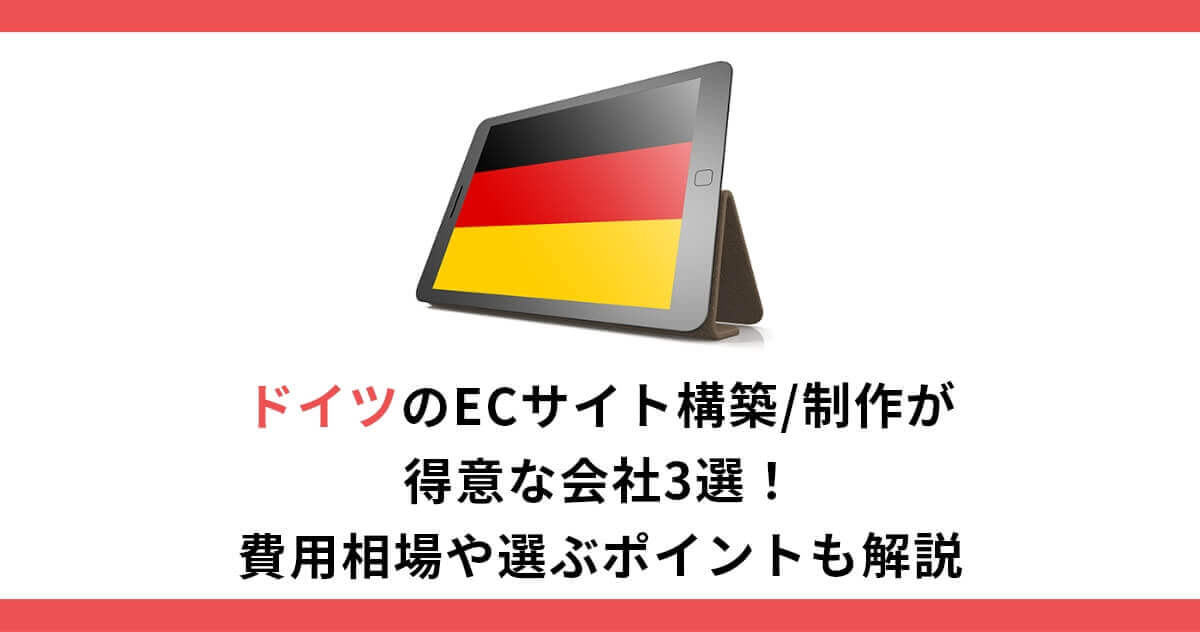





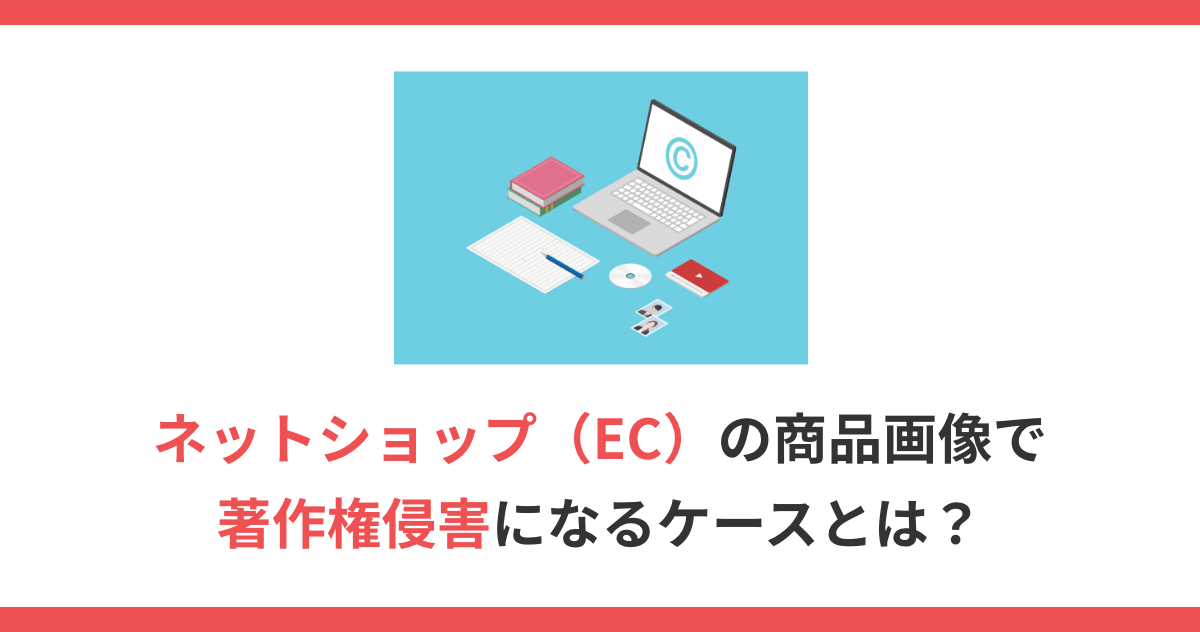






 に相談する
に相談する 